MBTI診断を受けるたびに結果が毎回違う、どれもしっくりこない、なんだか違う気がする…。こんなふうにMBTIが定まらないと悩んでいませんか?
一度だけならまだしも、何度やっても合ってない気がして、どのタイプにも納得いかない。
「もしかして2つ持ちなのでは?」「自分がないのかも」と不安になってしまう方も少なくありません。
実際、MBTIは非常に奥深く、4文字のタイプだけで自分の本質を語るのは簡単ではありません。例えば一番レアなMBTIや一番少ないMBTIとされるタイプは、診断でも出にくい傾向があり、誤認や自己理解のズレが生じやすいのです。中には「不人気?」「嫌われ者?」なんて不安を抱く人も。
しかし、だからといってMBTIが意味のないものというわけではありません。むしろこの違和感の中に、あなただけの個性と多様性が隠れています。
この記事では、MBTIが定まらない理由を徹底解説し、本当の自分を見つけるための視点とヒントをわかりやすくご紹介します。
- MBTI診断が毎回違う理由がわかる
- 結果がブレる人の傾向と特徴を知れる
- 違和感がある時の対処法を学べる
- 心理機能を使って自己理解を深められる
MBTIが定まらないと悩む人へ
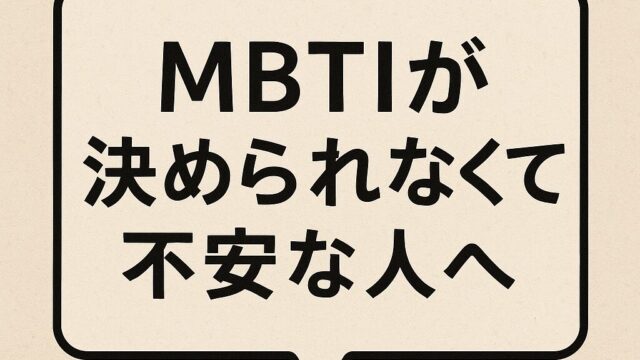
- MBTI診断で結果が毎回違う理由とは?
- MBTIで毎回違う人の共通点と傾向
- MBTIが違う気がする時の対処法
- MBTIが合ってないと感じる本当の理由
- MBTIが納得いかない時に見直すべき視点
- MBTIが2つ持ちと感じる人はどう考える?
MBTI診断で結果が毎回違う理由とは?
MBTI診断を受けるたびにタイプが変わってしまう…という現象は、意外と多くの人に見られます。これは「自分ってどんな人間なんだろう?」と深く向き合っている証でもあるのですが、なぜこんなに変わるのか、ここではその背景を解説します。
診断形式によって結果が変わる
まず知っておいてほしいのが、MBTI診断には公式と非公式のテストがあるという点です。特に有名な16Personalitiesは、MBTIに似ていますが、ビッグファイブ理論をベースにした別物。ここで得られるタイプは、ユングの理論とはズレがある場合があります。
心理状態による影響
次に注目すべきは、その時の感情や精神状態。ストレスが多い日や、落ち込んでいる時に受けた診断は、普段のあなたとは異なる回答を引き出すことがあります。特に「社交性があるか?」という質問では、気分の波が影響しやすく、E(外向)とI(内向)が逆転することも。
自己認識の揺らぎ
自己分析に慣れていない場合、「こういう自分でありたい」と思う理想像で答えてしまうことがあります。これは心理学でいう「理想自己」の反映であり、診断結果のズレにつながります。特にF型やN型に多く見られる傾向です。
質問の曖昧さと翻訳の問題
MBTI診断は英語圏で生まれたため、日本語に翻訳された際の微妙なニュアンスの違いが、選択肢の判断を難しくしています。「あなたは計画的ですか?」という質問も、文化や場面によって捉え方が変わります。
心理機能の発達と成長
ユングの理論では、人は心理機能を発達させていく存在とされています。そのため、年齢を重ねるにつれて、自分の「利き手」ではない機能も自然と使いこなすようになり、診断の結果に変化が出るのです。
まとめずにポイント
つまりMBTIが毎回違うのは「不安定だから」ではなく、「柔軟で多面的だから」。それを前提に、自分を観察することが大切です。
MBTIで毎回違う人の共通点と傾向
では実際、MBTIの結果が毎回変わる人たちには、どんな特徴や傾向があるのでしょうか?ここではその「共通点」を見ていきましょう。
タイプのスコアが中間寄り
MBTI診断では各指標において、「E50%/I50%」のようなボーダーライン上の数値が出ることがあります。これはちょっとした気分の変化でもタイプがひっくり返る原因になります。診断結果を数値で見られるテストを利用すると、より自覚しやすいです。
ペルソナを多用する性格
社会や家庭での役割によって「外向的に振る舞う」「感情を表に出さない」などの仮面=ペルソナを使い分けている人は、診断時にどの自分で答えればいいか迷いがちです。これは特にINFJやENFPなど、環境適応力の高いタイプに見られる傾向です。
自己分析が浅いor慣れていない
「直感的に答えてください」と言われても、自分の性格に自信がなければ、答えに迷ってしまいます。これはMBTI診断の自己申告形式が原因で、自分のことを深く理解していないと結果がぶれやすいです。
質問の意味を誤解している
「友達と話すのが好きですか?」という質問に、”気分が良い時は好き”と答えるか、”基本的には疲れる”と答えるかで大きく結果が変わります。質問の文脈をどう解釈するかでも結果にズレが出るのです。
共通しているのは「柔軟さ」
タイプが変わる人の多くは、複数の性格的要素を持ち、環境や状況に応じて適応することができます。これは決してネガティブなことではなく、むしろ「多面的な自分を持っている」と言い換えられます。
MBTIが違う気がする時の対処法
診断結果を見て、「え、これ本当に私!?」と違和感を覚えたこと、ありますよね?でも大丈夫、そんなときに試してほしい対処法を紹介します。
第一機能を基準に考える
MBTIのタイプは、4文字の組み合わせだけでなく心理機能の順番が大切です。例えばINTPであれば「Ti(内向的思考)」が主機能。子どもの頃から自然に使ってきた機能が何かを思い出すと、本来のタイプに近づきます。
幼少期の自分を振り返る
社会に適応する中で、私たちは「自分以外の性格」も演じるようになります。だからこそ、5〜10歳くらいの自分を思い出してみてください。どんなことでワクワクしていたか、何に夢中になったかが、主機能のヒントになります。
複数の診断を受けてみる
一つの診断に頼らず、時期やフォーマットを変えて複数のテストを受けてみると、共通する要素が見えてきます。例えば、無料と有料の両方を試すのもおすすめです。
タイプにとらわれすぎない
そもそもMBTIは、性格を断定するものではなく心のクセを観察するための道具です。違和感を覚えるのは、あなたが多面的で、環境によって柔軟に対応できるからこそ。診断結果に縛られず、自分自身を丁寧に見つめ直すことが大切です。
心理機能を一つずつ学ぶ
MBTIの背景には8つの心理機能があります。例えば「Se(外向的感覚)」や「Ni(内向的直観)」など。それぞれの意味を知ることで、自分にしっくりくる機能がどれかが見えてきます。タイプではなく、機能に着目してみると理解が進みます。
MBTIが合ってないと感じる本当の理由
MBTIを受けたものの「これ、自分じゃないかも…?」と違和感を覚えた方、意外と多いのではないでしょうか。そんな時、単に診断ミスだと片づけるのではなく、何がそう感じさせたのかを掘り下げてみましょう。
理想の自分像で回答している
MBTI診断はあくまで「今のあなたが自認している傾向」を拾い上げます。そのため、「こうなりたい」「この方が社会的に良さそう」といった願望が回答に混ざると、実際の性格とズレることがよくあります。
環境に適応しすぎている
たとえば本来は内向的(I)な人が、外向的(E)の役割を長年演じていると、外向寄りの結果が出ることがあります。社会的な仮面(ペルソナ)が、診断結果に強く影響するわけですね。
心理機能への理解不足
MBTIは4文字だけでなく、「心理機能の階層構造(主・補助・第三・劣等)」が大切。たとえばENTPの主機能はNe(外向的直観)ですが、これが理解できていないと表面上の言動に引っ張られて、別タイプに感じてしまうケースがあります。
使った診断の種類が違う
MBTIと称するテストは多数存在しますが、特に「16Personalities」は公式MBTIとは別物です。こちらはビッグファイブ理論をミックスした内容のため、MBTIらしさに欠けると感じる人も。
ライフステージによる変化
若い頃は感覚的(S)だったけど、社会経験を重ねて直観的(N)にシフトする人も。MBTIは「生来の認知スタイル」を見ているため、現在の振る舞いとギャップが生じることもあります。
MBTIが納得いかない時に見直すべき視点
「MBTIの結果がどうしても腑に落ちない」そんなときに必要なのは、再診断ではなく「視点の見直し」。誤解や偏りを正すだけで、意外とスッキリすることもあります。
主機能を起点に考える
MBTIのタイプ判定は主機能(最も自然に使う認知機能)が中心です。例えばISTJなら主機能はSi(内向的感覚)。その主機能を、人生の中でいつ・どんな風に使っていたかを見つめてみましょう。
幼少期の記憶をたどる
大人になると、環境や社会的立場に応じた性格が表に出ます。子ども時代に何を好み、どんな視点で世界を見ていたかが、MBTIタイプにおける判断材料としてかなり重要です。
補助・第三機能とのバランスを見る
MBTIタイプは単体ではなく、4つの心理機能の構成で考えます。補助機能(第2機能)や第三機能が強く表出していると、主機能と混同してしまい、結果がズレて感じられることもあります。
日常のストレス状態を確認
強いストレスや不安を抱えているとき、普段は使わない「劣等機能」が過剰に出ることがあります。これをグリップ現象と呼び、普段の自分とは異なる傾向が表れがちです。
診断結果を「固定概念」で見ない
MBTIタイプに対して「このタイプはこうあるべき」と思い込むと、納得できないことが増えてしまいます。タイプごとの特徴は傾向であって絶対ではありません。
MBTIが2つ持ちと感じる人はどう考える?
「自分、INFPのときもあればINFJにも見える…」そんなふうに複数のMBTIタイプが当てはまる感覚を持つ人、実はかなり多いんです。これは間違いではなく、むしろMBTIをよく理解しようとするほど出てくる悩みの一つ。
タイプの似たペアに要注意
INFPとINFJ、ENTPとENFPなどは非常に似ており、主機能と補助機能の順序が逆なだけ。表面上の行動や性格が似ているため、どちらなのか迷いやすいペアです。
環境適応による揺らぎ
学校・職場・家庭で求められる役割が変わると、その場に適した機能が強調されるようになります。一時的に他タイプのような性格になっているように見えるのは、よくある現象です。
NeやNiなどの多機能ユーザーも
例えば、Ne(外向的直観)とNi(内向的直観)のどちらも使える人は、自覚的に両方の世界観を持っていると感じます。全員が8つの心理機能を持っており、特定の場面で「他タイプ的」になるのは自然なことです。
4文字よりも心理機能で判断する
どちらのタイプなのか決めきれない場合、自分が一番自然に使っている心理機能は何かを突き止めるのが近道です。4文字だけでなく、機能優先でタイプを絞るのもおすすめです。
タイプに「縛られすぎない」意識も大切
MBTIは分類ではなく、あくまで思考や行動の傾向を知るツールです。「自分はこのタイプじゃなきゃダメだ」と思わず、柔軟に捉えてOKです。
MBTIが定まらないタイプを特定する方法
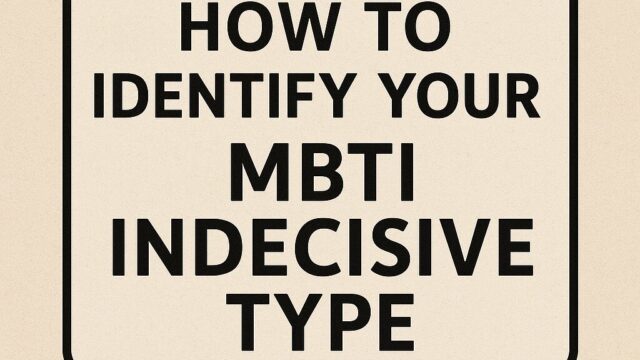
- MBTIで自分がないと感じる人の正体
- 第一・第二機能から見るMBTIの本質
- 第三・第四機能から性格タイプを深掘り
- 一番レアなMBTIとは?その特徴と誤認されやすさ
- 日本で一番少ないMBTIタイプはどれ?
- MBTIの変化は成長か?環境の影響か?
- MBTIが定まらないまとめ
MBTIで自分がないと感じる人の正体
MBTI診断をして「なんだか自分というものがよくわからなくなった…」と感じたことはありませんか?この感覚、実は非常に多くの人が抱いているものなんです。MBTIに取り組めば取り組むほど、迷いが生まれるという矛盾。その正体を、心理学の観点から解き明かしていきましょう。
自我とMBTIのギャップ
MBTIは、私たちの「思考の傾向」や「行動パターン」を示すモデルです。ですが、「私はこういう人間だ」と思い込んでいたイメージと、MBTIの診断結果が食い違うと、自分という存在がブレて感じられることがあります。これは、自我(アイデンティティ)と診断結果がうまく接続されないために起こる現象です。
社会的仮面(ペルソナ)の影響
「自分がない」と感じる原因の多くは、外部環境に適応するために築いた仮面にあります。たとえば、本当は内向的な人が外向的な環境で長く過ごすと、「自分ってどっち?」と混乱しがちに。これは、ユングが提唱したペルソナの概念と深く関係しています。
未発達な機能による違和感
MBTIでは4つの主要な心理機能があり、主に使うものと、苦手なものが存在します。このバランスが偏っていたり、無意識に抑圧している機能があると、自己理解がうまく進まず、「自分が空っぽ」と感じることもあるのです。
診断の表層だけを信じている
4文字だけのMBTI診断に頼ると、深層心理の複雑な構造を見落としてしまいます。特にオンライン診断の中には、質問が簡易すぎて信頼性が低いものもあるため、MBTIの全体像や理論構造をきちんと理解することが重要です。
感情を言語化しにくい人も注意
感情を認識・言語化する力(アレクサイミア傾向)が弱い人は、「自分がない」と感じやすい傾向があります。そうした方は、MBTIの結果を自己理解の“ヒント”として活用し、無理に当てはめようとしないことが大切です。
第一・第二機能から見るMBTIの本質
MBTIの診断結果には4つのアルファベットが並びますが、それだけでは本質が見えてきません。大切なのは「第一機能(主機能)」と「第二機能(補助機能)」の組み合わせ。これが、その人の物事の見方・判断の軸を決定づける核となります。
第一機能:性格の中心軸
MBTIでは、第一機能こそが「その人らしさ」を表す最重要要素とされています。たとえば、ISTJの第一機能はSi(内向的感覚)。これは過去の経験や実績に基づいて行動する傾向を意味します。第一機能は無意識レベルで自然に使われているため、自覚しにくい点もポイントです。
第二機能:第一機能を支える相棒
補助機能とも呼ばれる第二機能は、主機能をバランス良く補う存在。例えば、INFJの場合は主機能Ni(内向的直観)、補助機能Fe(外向的感情)で構成されており、深い洞察と他者への共感力を併せ持っています。ここでバランスを崩すと、性格的な偏りやストレスが表れやすくなります。
主・補助のバランスが「その人らしさ」
第一機能だけではなく、補助機能との協調があってこそ、安定した性格が育まれます。片方に偏りすぎると、人間関係や意思決定で迷いが増えるため、両者の役割を理解しておくことが自己理解を深める近道です。
第一機能を見極めるヒント
自分のタイプに迷ったときは、まず「自然に使っていて、疲れない行動や考え方」を振り返ってみましょう。それが主機能のヒントになります。
第三・第四機能から性格タイプを深掘り
MBTIの主役は第一・第二機能と思われがちですが、第三機能と第四機能(劣等機能)も見逃せません。これらは「裏の顔」とも言える存在で、意識下での動きが性格の奥深さや矛盾を生み出しています。
第三機能:発達途上の個性
第三機能は「影響はあるけど、まだ未熟」な部分を表します。例えば、ENFPの第三機能はTe(外向的思考)。これは論理的に物事を構築する能力ですが、主・補助よりも発達が遅いため、使い方にムラが出やすいのが特徴です。
第四機能:無意識に影響する影の要素
「劣等機能」とも呼ばれる第四機能は、無意識下にあって普段はあまり意識されません。ですが、ストレスが強まったときに一気に表に出てくることがあり、これをグリップ現象といいます。
第三・第四機能は人生の後半に育つ
心理学的に見ると、これらの機能は30代以降に徐々に意識化されると言われています。つまり、若い頃には自分でも気づかない影響を受けている可能性があるということですね。
性格の矛盾はこの2つが作る
人間関係でのジレンマや、ある場面でだけ自分らしくない行動をしてしまうのは、第三・第四機能の影響が大きいから。これらの存在を意識することで、「なぜこんな風に感じるんだろう?」というモヤモヤが整理されることもあります。
一番レアなMBTIとは?その特徴と誤認されやすさ
MBTIタイプの中で「一番レアなタイプは何?」と気になる方も多いのではないでしょうか。統計的に最も稀少とされるのが『INFJ(内向・直観・感情・判断)』タイプです。全人口の1〜2%程度といわれており、その希少性ゆえに誤解されやすいタイプでもあります。
INFJの特徴とは?
INFJは「静かな理想主義者」とも呼ばれます。直観力と深い共感性、そして一貫した価値観を持つ内向型で、人との関わりに慎重ながらも使命感にあふれた行動をとる傾向があります。主機能はNi(内向的直観)、補助機能はFe(外向的感情)です。
誤認されやすい理由
INFJは、感情を表に出しすぎず、思考も論理的な面を持つため、INTJ(内向・直観・思考・判断)やINFP(内向・直観・感情・柔軟)と混同されやすいという傾向があります。また、外的適応力も高く、環境によって外向的に見えることがあるため、自身でもタイプ判別が難しくなることがあります。
直観的な判断と誤診断
INFJは、直感を頼りに未来や本質を見抜く力がありますが、質問項目が抽象的な診断ツールでは、それが正確に反映されないことも。結果として間違ったタイプが出るケースも少なくありません。
レアなタイプの自己理解における注意点
稀少タイプであることにこだわりすぎると、逆に自己理解が歪む場合もあります。重要なのは、そのタイプでどう生きるかであって、珍しいかどうかではありません。
日本で一番少ないMBTIタイプはどれ?
さて、世界的に見てINFJが最も少ないとされますが、日本における最少MBTIタイプはどうでしょうか? 実は、文化背景や教育環境が異なる日本では、世界とはまた違った傾向が見られます。
国内におけるMBTI分布の特徴
日本では外向よりも内向型が多く、また判断より柔軟性を持つP(Perceiving)タイプが増加傾向にあります。その中で特に少ないのがENTP(外向・直観・思考・柔軟)タイプといわれています。
ENTPが少ない理由
ENTPは、創造的で議論好き。新しいアイデアを次々と打ち出し、常識を打破していくタイプです。しかし、日本の教育や社会は、秩序・協調・安定を重んじる傾向が強いため、ENTPのような特性が育ちにくい環境にあるともいえます。
統計データが少ない課題
MBTIの日本での調査はアメリカほど詳細ではなく、公的な統計も不足しています。そのため、日本心理学会などの信頼できる機関を参考にしつつ、海外との比較も交えて読み解く視点が重要です。
社会の変化と少数派タイプ
多様性が重視される今、これまで目立たなかったENTPや他の稀少タイプの活躍の場も広がっています。「少ない=劣っている」ではなく、「少ない=個性」ととらえましょう。
MBTIの変化は成長か?環境の影響か?
「あれ?前とタイプが変わってる…?」MBTIを何度か診断したことがある方なら、こんな経験があるかもしれません。果たしてこれは「成長」によるものなのか、それとも「環境」の影響なのでしょうか?
MBTIは変わるもの?
結論から言えば、MBTIの「中核タイプ」は変わりにくいです。しかし、行動や傾向に表れる表面的な部分は、環境やライフステージによって変化することがあります。
成長による機能の発達
心理学的には、30代以降に第三機能や第四機能が徐々に意識化されてきます。これが、以前より柔軟な思考や新しい判断傾向として現れ、「タイプが変わった」と感じる原因になるのです。
環境適応による一時的な変化
また、職場環境や人間関係によっても「演じる」性格が生まれます。例えば、内向型の人が営業職で外向的に振る舞っていれば、診断では外向型に出ることもあります。
タイプ変化の見極め方
本当に変わったのか、一時的な変化かを見極めるには、長期的な自己観察と記録が役立ちます。また、単なるオンライン診断だけでなく、専門家による面談型のMBTI診断もおすすめです。
日本キャリア開発協会など、信頼性のある認定機関の診断を受けると、より正確な自己理解に繋がります。
MBTIが定まらないまとめ
- 診断形式の違いでMBTIが変化
- 心理状態により結果が揺れる
- 理想の自分像で答えてしまう
- 言語や文化の影響で解釈がズレる
- 年齢と共に心理機能が発達する
- タイプ中間の人は診断が揺れやすい
- ペルソナ使用者は混乱しやすい
- 自己認識が浅いと回答が不安定
- 質問の解釈次第で答えが変わる
- 複数タイプの要素を持つ柔軟な人
- 主機能を意識してタイプを絞る
- 幼少期の行動を振り返るのが有効
- 心理機能を個別に学ぶと納得できる
- 稀少タイプは誤認しやすい傾向あり
- タイプに縛られず柔軟に捉えるべき







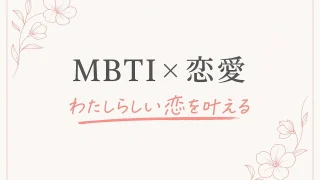
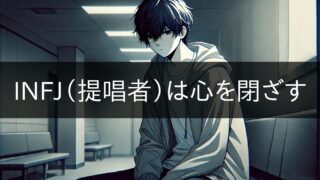
![INTJ (Architect) Love [Male Edition]](https://personality-mbti.com/wp-content/uploads/2025/02/INTJ-Architect-Love-Male-Edition-320x180.jpg)

